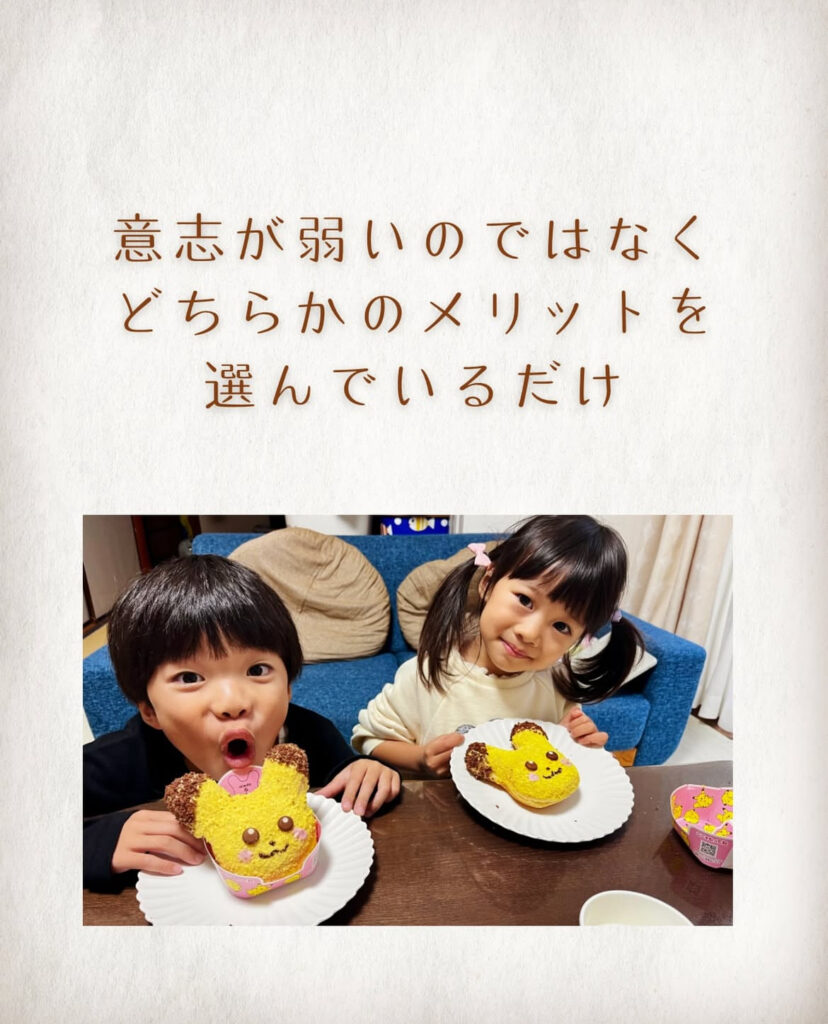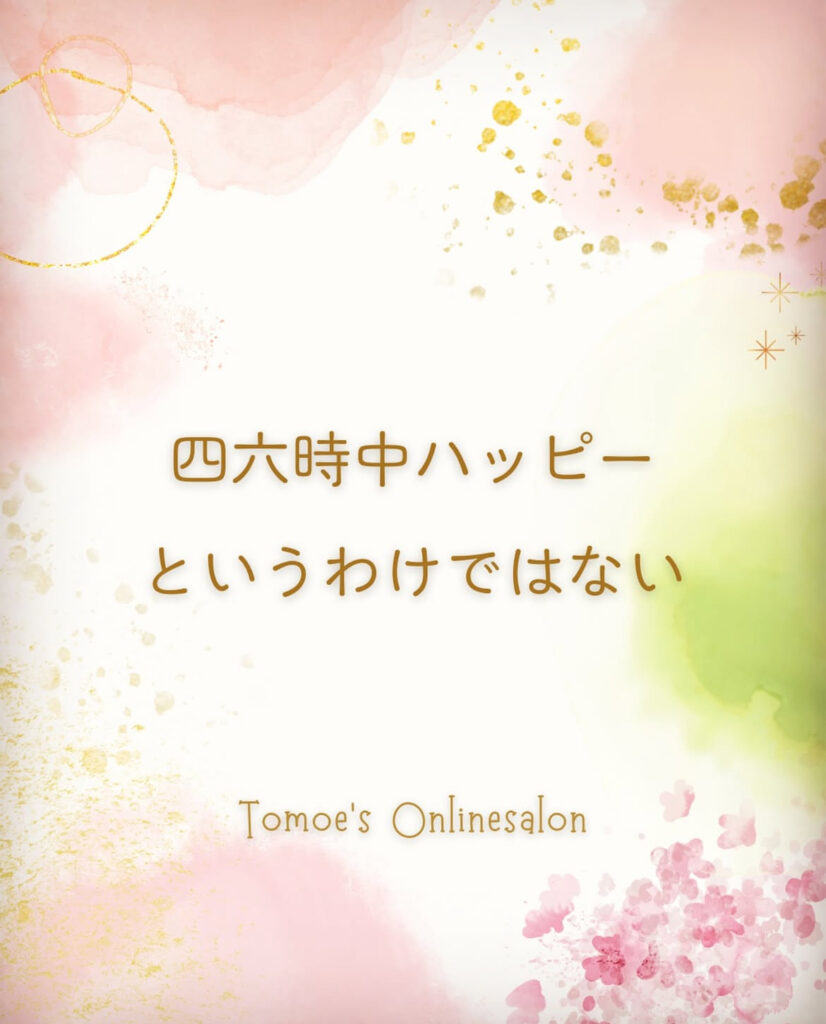こんにちは。
『個性』と『言葉』を味方にして、自分と家族の心の土台を整える個育て講師の土屋 美保です。
「仕事も子育ても欲張りたい」
「自分を大切にしたい」
—そんな頑張るママたちへ。
このブログでは、自分自身の土台を整える方法や、個性に合った子育てのコツを、個性學(こせいがく)の視点からお伝えしていきます。
今回は、前回少し触れた「3分類」をさらに深掘りした「12分類」についてです。
自分と周りの人たちの個性を知り、より良い人間関係を築くヒントにしていただけたら嬉しいです。
個性學の12分類とは?違いは「強み」と「役割」
前回のブログでご紹介した「3分類」を、それぞれさらに4つに細分化したものが「12分類」です。
これは、一般的に通常性格と言われる分野で、行動や意思決定の特性が分かります。
12分類の違いは、強みや役割の違いを示しています。
それぞれの個性に注目すべき特徴があり、それを活かして社会で役割を果たすことで、社会全体がスムーズに回っていく、というのが個性學の考え方です。
この違いを、梅の花で例えてみましょう。
大きな分類では、全て「梅」という花です。
しかし、梅の中にも「玉梅」や「月世界」など、たくさんの種類があります。パッと見は似ていても、色や形、育て方が微妙に違います。
この「種類」の違いこそが、個性學の12分類が示していることです。
欠点ではなく、良さ。誰もが持つ個性という才能。
梅の花の例でいえば、「この種類は育てにくい」といった特徴はあるかもしれませんが、「これは良くない」「ダメな梅だ」といった種類は存在しません。
梅の花には梅の花の良さがあり、桜の花には桜の花の良さがある。
松の木には松の木の良さがあり、竹には竹の良さがある。
ソメイヨシノと枝垂れ桜、どちらもそれぞれに美しい。
アカマツもクロマツも、華やかさはないかもしれないけれど、存在感があり風情がある。
要は、「優劣」や「正解」は存在しない、ということです。
なれないものになろうとしなくていい
このたとえ話で伝えたいのは、「それぞれに特徴があり、それぞれに良さがある」ということです。
もちろん、良いところばかりではないかもしれませんが、だからといって、誰も松の木に桜の花を咲かせようと頑張らせたりしません。
また、咲いている梅の花に向かって、
「松みたいにシンプルになれ」と言うこともありません。
白の梅の花が、赤の梅の花でないと「梅ではない」と悩む必要はないのです。
これは、私たち人間の世界でも全く同じです。
私たちは皆「人」という大きな分類に属する同じ人間ですが、どんな個性を持って生まれてきたのかは、遺伝性もなく、見た目では分かりません。
個性學は、この「生まれ持った素質や特質」を知るための強力なツールなのです。
個性學は「人を分ける」ためのものではない
個性學は、自分や他人の個性を正しく知ることで、人間関係やコミュニケーションを改善することができる学問です。
しかし、個性學は決して人を分けるためのものではありません。
私たちは、個性だけでなく、経験、環境、親の影響、感情、思考など、様々な要素で構成されています。
個性學は、その中の「持って生まれたもの」を知るためのツールに過ぎません。
だからこそ、個性學で個性を正しく知り、受け止め、受け入れ、共に生きていくという姿勢が大切になります。
自分自身を知ることは、自分を大切にする一歩。
そして、回りの人たちを知ることは、子育てや仕事、日常のコミュニケーションを円滑にする鍵です。
このブログを読んで、個性學に興味を持っていただけたらとても嬉しいです。
いつもありがとうございます。
カテゴリー一覧

「午後の紅茶を午前に飲む」から始まった、私の2026年のワクワクリスト時間

保育園児のママに知ってほしい「うちの子だけ?」を乗り越えた、心が軽くなる子育ての答え